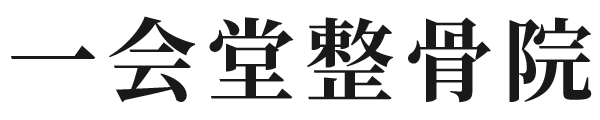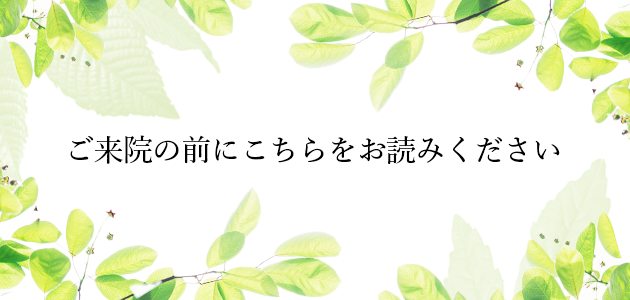営業時間のご案内
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
| 16:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ✕ |
お知らせ
NEWS
代表あいさつ
初めまして、一会道
代表 岡村弘樹です。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、対処療法で一時的に痛みを感じなくさせるのではなく、
身体を整え根本的な病(やまい)の原因を探す事を目指しております。
本当に身体を良くしたい方のための調整法です。
一会道は心と身体を整えていくことが目的です。
心と身体を整えることで、病気、苦痛、不安、恐怖、霊的、その他、からの解放に向かいます。
一会道は、心と身体の問題から様々な問題が引き起こされていることに、気づいて頂くための心身療法です
武道を通して生み出した独自の施術は20年以上の施術実績で、近隣の方だけではなく遠方からもお越しいただく施術です。
代表 岡村 弘樹
当院の特徴
FEATURE

他との一番の違い。それは、カウンセリングを重要視していることです。
心、身体、両方から観ていきます。
当院では患者さんに十分ご納得いただいた上で施術をうけていただきたいと考えています。
病いを生み出した、根本は、心の奥底にあります。深層心理ともいいますが、その部分を観ていく事が重要です。
そして病気や痛みの理解力をあげるのが目的です。その部分に気づいて頂くための調整が私の役割です。

無痛で安心
安全な施術法です。
骨格のゆがみを調整するというと、一般的にイメージされるカイロプラクティックのような強い刺激を与えたり、矯正を行うように思われがちです。
しかし当院の施術法は、痛い場所を触らないソフトな施術です。
乳児や妊婦、骨粗鬆症のご老人も安心して施術が受けられます。
揉まずに痛みの少ない施術を体験したい方はご来院ください。
逆に、グイグイ押したりバキバキ骨を矯正したりと、強い刺激を求めていらっしゃる方には向かない施術法です。

湿布などの対処療法は行いません
マッサージのような癒しではありません
「腰痛」「肩こり」「頭痛」の時などに処方される湿布や痛み止めの説明書には「病気そのものを治すものではなく、病気によるいろいろな症状や苦痛をやわらげる薬です。」と書かれています。
当院ではそのような対処療法は行いません。
施術案内
MENU

カウンセリング・ヒーリング

手技療法

遠隔治療
症状一覧
SYMPTOM
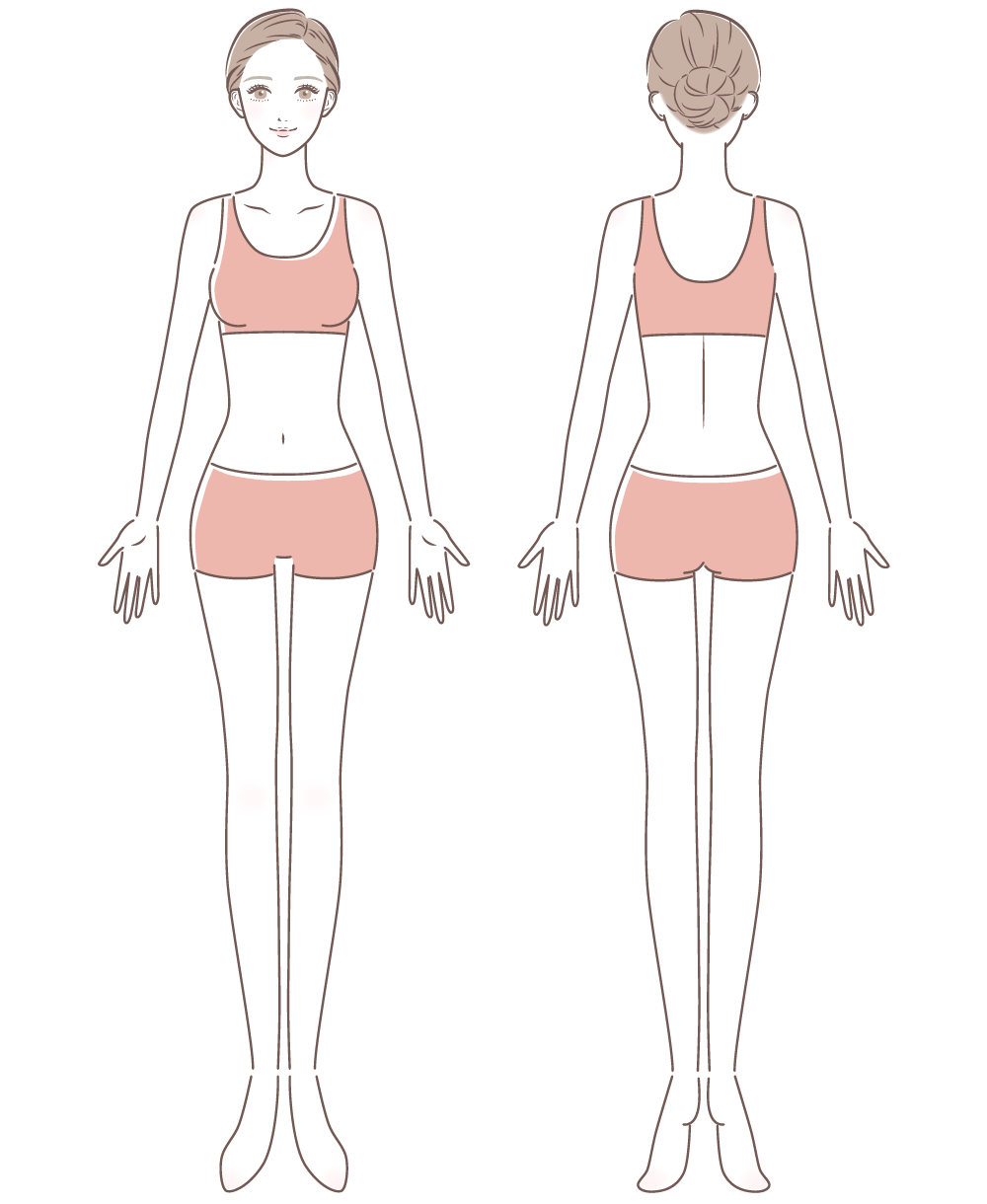
頭
首・肩
腰
膝・足
その他
新着コラム
COLUMN

眼精疲労

慢性頭痛の予防法について

頭痛の日常生活で行える対処法と予防法について

骨盤歪み原因

骨盤矯正

群発頭痛

偏頭痛

自律神経は失調しない!?
当院のご紹介
ABOUT US
一会堂整骨院
- 住所
-
〒108-0073
東京都港区三田2-14-7 406
- 最寄駅
-
都営三田線
三田駅A8出口から徒歩4分
JR田町駅から徒歩6分
- 駐車場
-
なし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ✕ | ✕ |
| 16:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ✕ |
- お電話でのお問い合わせ
-
09065313358